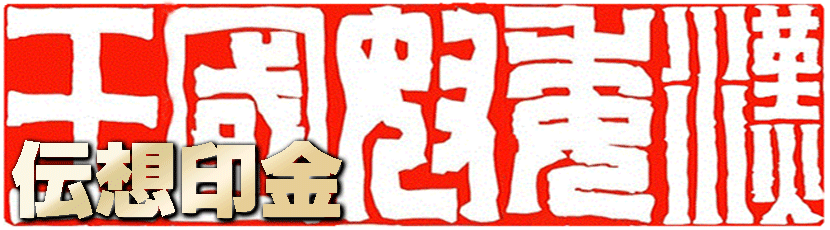
■後漢初代皇帝から奴国王へ送られた金印■
1784年、志賀島の田地で側溝の整備をしていた地元農民によって金印が発見されます。
金印は儒学者・亀井南冥に鑑定依頼されますが、南冥は中国南北朝・宋の時代に書かれた「後漢書」に記される
「建武中元二年(西暦57年)、倭の奴国、貢を奉じて朝賀す。使人は自ら大夫と称す。倭国の極南界なり。光武、賜るに印綬を以ってす。」
という文章に注目し、この金印は「後漢書」に記載される印綬に違いないと鑑定します。
この西暦57年の出来事は卑弥呼の時代より約180年ほど前の事で、国外の書物に残る福岡の歴史で一番古い出来事になります。
その後、金印には贋作論が出され議論が繰り返されますが、1931年には重要文化財に、1954年には国宝に指定されています。
■漢委奴国王印年表
|
B.C.100年前後
|
前漢七第皇帝の武帝(劉徹)より?王に金印「?王之印(てんおうのいん)」が送られたと推測される。
|
|
57年
|
後漢初代皇帝の光武帝(劉秀)より奴国王に金印が送られる。(後漢書の記述内容)
|
|
58年
|
光武帝の第九子・劉荊が廣陵王に封じられた際に金印「廣陵王璽(こうりょうおうじ)」を受領する。
|
|
239年
|
卑弥呼が魏に使者を遣わし「親魏倭王」の金印を受ける。(三国志の記述内容)
|
|
200年代後半頃
|
晋の陳寿(ちんじゅ)によって「三国志」が書かれる。
「三国志・倭人の条(魏志倭人伝)」には「漢の時に朝見する者あり」と記載される。
|
|
400年代前半頃
|
南北朝時代の南朝・宋の范曄(はんよう)によって「後漢書」が書かれる。
|
|
1784年
|
2月初旬 修猷館、甘棠館が開校。
2月23日 志賀島の田地で金印が発見され、亀井南冥により「後漢書」に載る金印と鑑定される。
|
|
1792年
|
亀井南冥、甘棠館・館長の座を追われる。
|
|
1956年
|
中国雲南省の墳墓で蛇鈕・「?王之印(てんおうのいん)」が発見される。
この印の鈕(取っ手)は「漢委奴国王印」と同じ蛇鈕。
|
|
1981年
|
江蘇省より「廣陵王璽(こうりょうおうじ)」が発見される。
この印は「漢委奴国王印」の製作工法と多数の類似点が指摘される。
|
■関連記事
$no=1485;
include("./ppg/post/articleoutonce.php");
?>
$no=1526;
include("./ppg/post/articleoutonce.php");
?>
$no=2032;
include("./ppg/post/articleoutonce.php");
?>
$no=2078;
include("./ppg/post/articleoutonce.php");
?>
$no=1644;
include("./ppg/post/articleoutonce.php");
?>
$no=2080;
include("./ppg/post/articleoutonce.php");
?>
$no=1637;
include("./ppg/post/articleoutonce.php");
?>
$no=1640;
include("./ppg/post/articleoutonce.php");
?>
$no=1741;
include("./ppg/post/articleoutonce.php");
?>
$no=1476;
include("./ppg/post/articleoutonce.php");
?>
$no=1483;
include("./ppg/post/articleoutonce.php");
?>
$no=1648;
include("./ppg/post/articleoutonce.php");
?>
$no=856;
include("./ppg/post/articleoutonce.php");
?>
$no=1659;
include("./ppg/post/articleoutonce.php");
?>
$no=320;
include("./ppg/post/articleoutonce.php");
?>
|  ';
echo $res;
?>
';
echo $res;
?>
 ';
echo $res;
?>
';
echo $res;
?>
 ";
echo $res;
?>
";
echo $res;
?>